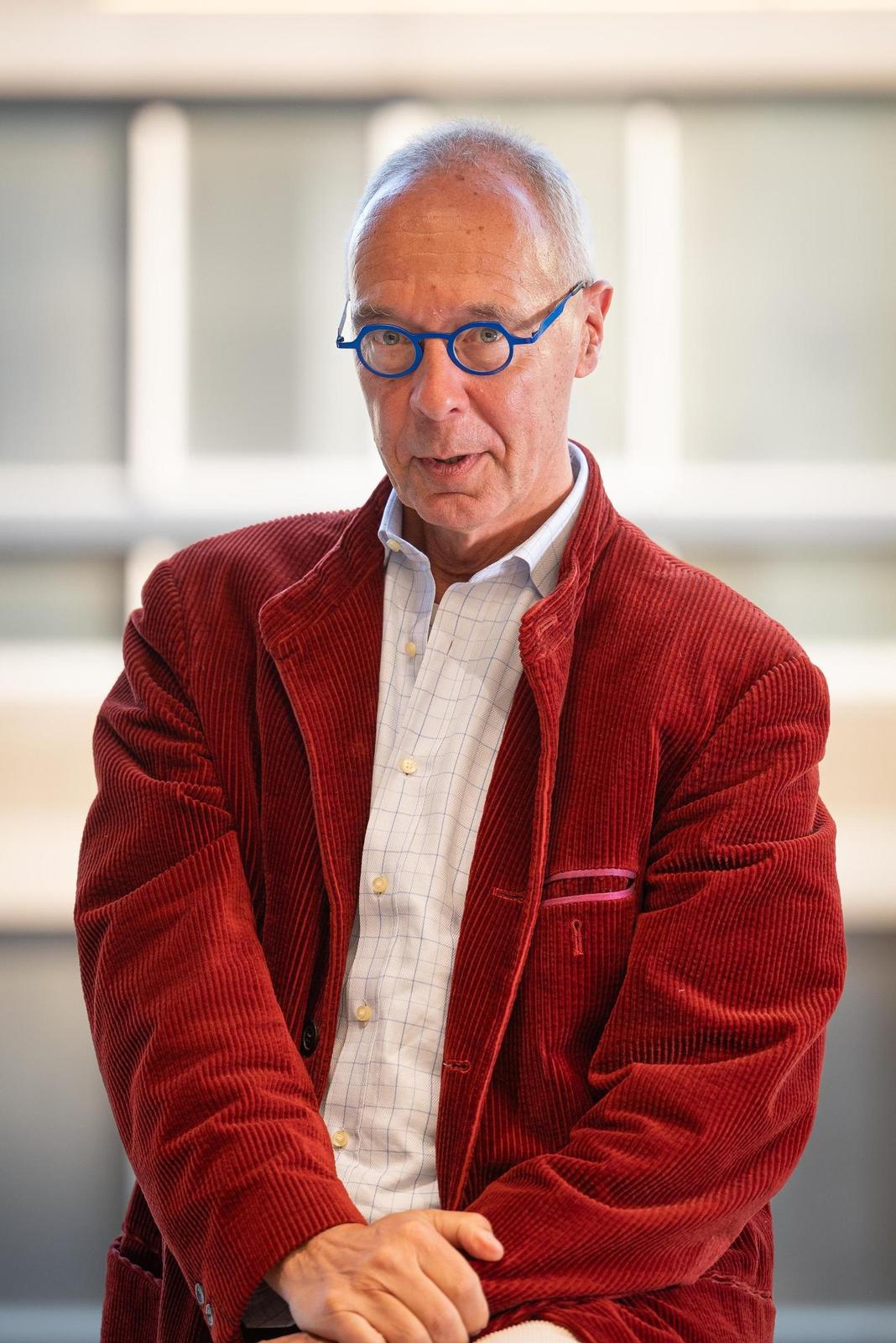変化する世界における金融リーダーとしての東京の地位
1月24日、日本橋兜町にあるKABUTO ONE ホール&カンファレンスにてFinCity Global Forum 2025が開催された。このフォーラムでは、加速度的に変化する国際金融の世界で東京がどのように進化し、その座を維持していくべきかをテーマにして、一連のプログラム、パネルディスカッション、ピッチセッションが行われた。冒頭では、小池都知事による開会あいさつがあり、その後、イェスパー・コール氏がモデレーターを務める「2025年国際金融・経済政策の見通しと金融センターとしての東京の役割」と題した基調対談が行われた。この基調対談には、一般社団法人東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)会長の中曽宏氏と、現在はアジア開発銀行総裁である元財務省高官の神田眞人氏が出席した。
ドイツ出身のコール氏は、欧州と米国で学士号、修士号を取得し、1986年に来日。現在はマネックスグループおよびカタリスト投資顧問株式会社(日本初の個人投資家向け企業エンゲージメント投資・活性化ファンド)のエキスパートディレクターを務めている。「国際金融都市・東京アドバイザリーパネル」を含む日本政府や企業の諮問委員会で複数の役職を歴任しており、 FinCity.Tokyoアンバサダーにも任命されている。

世界的な変化が東京の金融業界にチャンスをもたらす
コール氏は対談の冒頭で、今は従来よりも貿易ルートや資本の流れが多様化し、「現在の世界経済は分断化が進んでいます」と指摘した。さらに、パネルディスカッション後のインタビューでは次のように補足した。「過去30年ほどは、貿易や資本の成長がグローバルに拡大する時代でした。かつては、G7のような明確な経済ブロックがあったため、世界は比較的シンプルでしたが、今は貿易も資本も複雑に分断化が進んでいます」。貿易の分断化は、世界経済に課題を引き起こしているが、一方で新たな機会も生み出している。コール氏は、特に日本はこの新しいチャンスと国際貿易の変化を最大限に活用できる立場にいると見ている。
日本が強みとしてアピールできる点は何だろうか。「とてもシンプルです。2つあります」とコール氏は言う。「1つ目は、日本の資産は世界的に著しく割安で、投資の参入障壁が非常に低く抑えられること。2つ目は、非常に裕福な国であること。日本は金融資産が豊富でありながら、多くの金融資産が十分に活用されず眠っています。この「休眠資産」こそが、信じられないほどの可能性を秘めているのです」
コール氏は、日本において価格が手頃なものの例として住宅を挙げた。「日本で安い住宅を探せば、たくさん見つかります。ヨーロッパでもアジアでもアメリカでも、日本と同じ値段で買える住宅はありません」
政府と金融業界の連携が結果を生む
資本が持つ経済作用の効用に東京都が注目していることは、コール氏にとって良い知らせだ。これまでにも、東京都や他の公官庁が特定の地域や産業の活性化の試みは行われてきたが、今回は一線を画す。すべての関係機関が共通の目標のもと結集しているからだ。東京都はこれら関係機関と連携し、リーダーシップを発揮している。
コール氏は、東京がリーダーシップを発揮するこの協力体制は、必然であったと見ている。「個々の取組や政策を切り取って、それぞれの効果を評価することには意味がありません。というのも、日本では、場当たり的に政策をやってきたことは一つもなく、中央政府や年金団体、その他の組織からの支援や協力体制のもと、驚くほど連携が取れているのです」。また、決定したことが覆されやすい他国に比べ、日本の意思決定力は強固である。「決定までは米国などよりもずっと時間がかかりますが、いったん決まると日本は一気呵成に物事が進みます」

コール氏が1986年に初めて目にした日本と、現在の状況は大きく異なっている。1986年までの数年間は、日本の金融業界にとって大きな転換期であった。1984年の日米円・ドル委員会と、それに続く1985年のプラザ合意により、円相場は市場に委ねられることになった。また、1986年には外国企業6社が初めて東京証券取引所の会員になることが認められた。「日本は、金利から商品、株式市場まですべての金融市場におけるこれら一連の規制緩和を取り組み始めました」
将来はどうなっていくだろうか。コール氏は、3~4年後には日本の中で世界に互するような本当のスター企業が生まれ、そういった企業によるM&A等で産業再編が加速し、国際金融センターとしての地位が向上することを期待している。「日本は今後も、堅調な経常黒字国であり、豊富な金融資産を有する債権国です。そして何よりも、サッカーでドイツ代表チームに勝ち続けるでしょう」と、彼は得意のジョークで締めた。
イェスパー・コール
写真/穐吉洋子
翻訳/浦田貴美枝